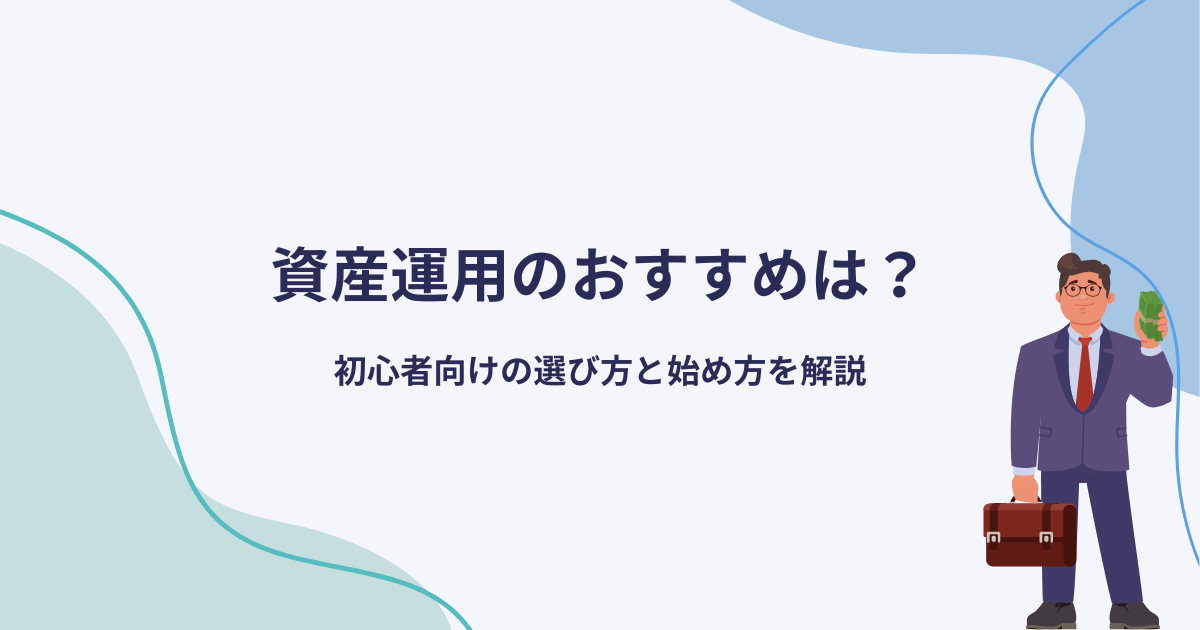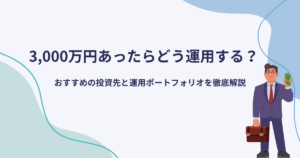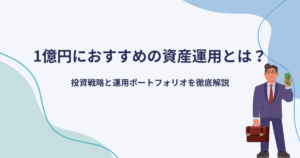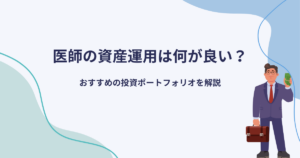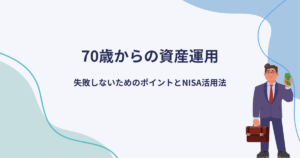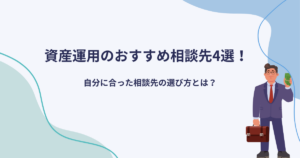- 何から始めればよいか分からず、最初の一歩が踏み出せない
- SNSで見かける情報が多すぎて、自分に合った運用方法が見極められない
- 制度や商品が複雑で、失敗しないか不安になっている
「資産運用を始めたいけれど、何を選べばよいか分からない。」そんな悩みを抱えていませんか。
新NISAやiDeCoといった制度、投資信託や国債といった商品、SNSで目にする情報の数々。選択肢が多すぎて、かえって動けなくなる方も少なくありません。
この記事では、運用初心者の方が迷わず資産運用を始められるよう、制度の基本から具体的な始め方まで、分かりやすく解説します。
読み終える頃には、あなたに合った運用方法が見えてくるでしょう。
資産運用を始める前に知るべき基本知識

資産運用を始める前に、押さえておきたい前提があります。
それは「目的を明確にすること」「リスクと期間の関係を理解すること」「生活防衛費を確保すること」の3点です。
ここでは、これらの基本的な考え方を解説します。
収益とリスクを理解する
資産運用における「リスク」とは、値動きの振れ幅のことです。リスクが大きいほど、大きく上がることもあれば、大きく下がることもある。そして一般に、期待できる収益が高いほど、リスクも大きくなるという関係があります。
たとえば株式は値動きが大きく、短期間で30%下落することもあれば、同じくらい上昇することもあります。
一方で個人向け国債は値動きがほとんどなく、元本が保証されていますが、その分リターンは控えめです。2025年10月時点では、個人向け国債の変動10年型で年1.08%程度、固定5年型で年1.22%程度となっています。
株式などの値動きのある資産は、短期で見ると価格のブレが大きく見えますが、10年・20年と長期で保有するとブレが小さくなり、安定しやすくなる傾向があります。
そのため、初心者の方は短期的な値動きに惑わされず、長期保有を前提に始めると良いでしょう。
インカムゲインとキャピタルゲインの違い
資産運用で得られる収益には、大きく分けて2種類あります。
- インカムゲイン
保有中にもらう収益のことで、利子や配当がこれに当たります。 - キャピタルゲイン
売買による値上がり益のことです。
たとえば個人向け国債では、半年ごとに利子を受け取れます。これがインカムゲインです。
一方、株式や投資信託を購入して価格が上がったときに売却すれば、その差額がキャピタルゲインになります。
インカムゲインを重視するからといって、安全性が確約されるわけではありません。配当も変動する可能性がありますし、債券も金利変動の影響を受けます。
初心者の方は、インカムとキャピタルの両方を合わせた総合リターンで考えるとよいでしょう。
資金計画を立てる
資金計画を立てるときは、次のステップで進めます。
毎月の生活費の3〜6か月分を預貯金として手元に置きます。万が一収入が途絶えても、当面の生活を維持できる金額です。
リボ払いやカードローンなど、金利が高い借入金がある場合は、資産運用よりも先に返済を優先しましょう。
手取り収入から生活費や貯金を差し引いて、いくら運用に回せるかを確認します。無理のない範囲で設定することが継続の秘訣です。
毎月の積立額と、ボーナス時などに拠出する一時金を分けて考えます。
「10年後に300万円」といった目標を設定し、年次で30%程度の下落があっても耐えられるかを確認します。
新NISAのつみたて投資枠や成長投資枠、iDeCoなど、どの制度をどう使うかを決めます。
このステップを踏めば、「毎月いくら積み立てるか」「いつから始めるか」「どの口座を使うか」が明確になります。
「月1万円から始めても大丈夫」という声もありますし、無理なく続けられる金額から始めることが大切です。
いくらから始められる?余剰資金の考え方
毎月の積立額は、手取り収入の5〜15%程度を目安にするとよいでしょう。たとえば手取りが25万円なら、月1.25万円〜3.75万円です。ただし家計状況は人それぞれですから、この範囲にこだわる必要はありません。
最初は月5,000円など少額からスタートし、3か月ごとに見直すのもひとつの方法です。ボーナス時には成長投資枠を使って一時金を拠出するなど、ライフスタイルに合わせて調整できます。
大切なのは、自動積立で習慣化することです。毎月決まった日に自動で買い付けられる設定にしておけば、手間もかからず、感情に左右されにくくなります。
目的・期限から必要利回りを逆算する方法
「10年で300万円を貯めたい」「毎月2万円ずつ積み立てる」といった条件が決まれば、必要な利回りを概算できます。具体的な計算式は複雑ですので、金融機関が提供するシミュレーションツールを使うと便利です。
利回りの目安は、インフレ率を参考にすると良いでしょう。2025年8月時点で、消費者物価指数(CPI)は前年比2.7%の上昇となっています。初心者の方は、インフレ負けを防ぐためにも、まず「3〜5%」を目指すとよいでしょう。
\ あなたに合うアドバイザーを診断 /
初心者におすすめの資産運用手段5つ

次に、初心者の方に向けて、基本となる5つの運用手段をご紹介します。
それぞれの特徴を簡単にまとめると、以下の通りです。
- 投資信託
複数の資産をまとめて、少額から購入できる仕組み - NISA
運用益が非課税になる制度。つみたて投資枠と成長投資枠の2種類がある - iDeCo(個人型確定拠出年金)
掛金が全額所得控除される一方、原則60歳まで引き出せない - 債券・個人向け国債
国や企業にお金を貸して利子を得る、比較的安全性の高い商品 - ロボアドバイザー
AIが自動で資産配分を提案・運用してくれるサービス
中でも初心者の方には、低コストのインデックス型投資信託を、新NISAのつみたて投資枠で定期的に積み立てる方法が、シンプルで始めやすくおすすめです。
それでは、各手段について詳しく見ていきましょう。
投資信託(インデックス投資)
投資信託とは、多数の資産をまとめて少額から買える仕組みのことです。投資家から集めたお金を、運用会社が株式や債券などに分散投資します。1つの商品を買うだけで、複数の銘柄に投資できる点がメリットです。
投資信託には大きく分けて2つのタイプがある
投資信託と一口に言っても、運用方法によって主に2つのタイプに分かれます。
- インデックス型
日経平均株価やS&P500といった市場の指数に連動することを目指す - アクティブ型
ファンドマネージャーが独自に銘柄を選び、指数を上回る成果を狙う
初心者の方には、インデックス型が特におすすめです。その理由は次の3つです。
- 分散が効きやすい
指数全体に投資するため、自動的に幅広い銘柄に分散される - 運用コストが低め
人の手による銘柄選定が少ない分、手数料が安い - 自動積立しやすい
シンプルな仕組みなので、長期の積立投資に向いている
2025年10月時点では、主要なインデックス型投資信託の信託報酬(運用管理費用)は年0.05%〜0.1%程度と、非常に低コストになっています。
たとえば「eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)」は信託報酬が年0.05775%、「eMAXIS Slim米国株式(S&P500)」は年0.09372%程度です。
商品を選ぶときは、コスト、連動する指数、純資産総額、つみたて投資枠の適格性などを比較しましょう。ご自身の目的やリスク許容度に合わせて選んでください。
ドルコスト平均法と自動積立の仕組み
ドルコスト平均法とは、定額で時間分散することで、平均取得単価を平準化する方法です。毎月同じ金額で買い続けると、価格が高いときは少なく、安いときは多く買うことになり、結果として平均購入価格が平らになりやすいのです。
ただし「必ず得をする手法」ではありません。相場が一方的に上がり続ける場合は、最初に一括で買ったほうが有利です。逆に下落が続く場合は、買い続けることで損失が膨らむ可能性もあります。
それでも初心者に積立投資が勧められるのは以下のような理由があります。
- タイミングを判断しなくていい
「今は高い?安い?」と悩む必要がありません。購入タイミングが分からない初心者でも迷わず続けられます。 - 感情に左右されない
相場が下がったときでも自動で買付。安い時に多く買えるチャンスを逃しません。 - 少額から始められる
まとまった資金は不要。月々1,000円といった少額から無理なく始められます。 - ほったらかしでOK
一度設定すればあとは全自動で買付。忙しい方や手間をかけたくない方に最適です。
相場の上下に一喜一憂せず、長期でコツコツ続けることが資産形成の基本です。積立投資は、その基本を自然に実践できる仕組みです。
NISA
NISAとは、投資で得た利益が非課税になる制度です。2024年から制度が大きく変わり、年間の投資枠と生涯の非課税枠が大幅に拡充されました。2025年10月時点の制度内容を整理します。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
|---|---|---|
| 年間投資枠 | 120万円 | 240万円 |
| 生涯非課税限度額 | 合計で1,800万円 (うち成長投資枠の上限は1,200万円) | |
| 投資対象商品 | 長期・積立・分散投資に適した 一定の投資信託・ETF | 上場株式、投資信託など (一部除外あり) |
| 投資方法 | 積立投資のみ | 一括投資・積立投資 |
| 非課税保有期間 | 無期限 | |
| 投資枠の再利用 | 可能 | |
| こんな人におすすめ | ・投資初心者の方 ・コツコツ長期で資産形成したい方 ・銘柄選びに時間をかけたくない方 | ・個別株や多様な投資信託に投資したい方 ・自分のタイミングで投資判断をしたい方 ・ある程度の投資経験がある方 |
つみたて投資枠と成長投資枠は併用できます。年間で合計360万円まで投資が可能です。
とはいえ、「枠配分や埋め方が難しい」と感じる方も多いでしょう。基本的には、つみたて投資枠を先に使い、成長投資枠は段階的に導入することをおすすめします。
つみたて投資枠と成長投資枠の使い分け
この2つの枠を効果的に使い分けるためには、それぞれの特性を活かして役割分担させることが重要です。
① つみたて投資枠:資産形成の「土台」を作る
まずはこの枠を使い、低コストのインデックス投資信託などを毎月コツコツ積み立てることから始めましょう。これにより、安定した資産の土台を築くことができます。
② 成長投資枠:資産を「上乗せ」する
こちらは、ボーナスなどのまとまった資金を投資したり、土台となる積立投資に加えて個別株に挑戦したりと、プラスアルファの投資をする際に活用します。
例えば、毎月の給料から3万円を投資に回せるなら「つみたて投資枠」で積立設定を行い、年2回のボーナスから合計80万円を投資できるなら、その分を「成長投資枠」で拠出する、といった使い分けが効果的です。
NISA口座で保有している商品を売却すると、その非課税枠が翌年以降に復活し、再利用できる便利な仕組みがあります。
ここで重要なのは、復活するのは売却時の価格ではなく、その商品を購入したときの価格(簿価・取得価額)だという点です。
- 例
-
100万円で買った投資信託が150万円に値上がりしたタイミングで売却した場合、翌年に復活する非課税枠は100万円分となります。
iDeCo
iDeCo(イデコ)は、将来の老後資金を自分で準備するための私的年金制度です。最大の魅力は、掛金の拠出時・運用時・受取時のそれぞれで手厚い税制優遇を受けられる点にあります。
一方で、iDeCoには「原則として60歳まで資金を引き出せない」というルールがあります。このため、老後を見据えた長期的な資産形成をしたい人におすすめの制度です。
最新の掛金上限額は次の通りです(2025年10月時点)。
- 自営業・フリーランス
月6.8万円(国民年金基金と合算) - 会社員(企業年金なし)
月2.3万円 - 会社員・公務員(企業年金あり)
月2万円(企業年金と合算で月5.5万円まで) - 専業主婦(夫):月2.3万円
- iDeCoの掛金上限額は、今後の税制改正で引き上げられる可能性があります。最新情報は、厚生労働省や各金融機関の公式サイトでご確認ください。
税制メリットと引き出し制限
iDeCoの税制メリットは以下の通りです。
- 掛金
支払った掛金は全額が所得控除の対象となり、毎年の所得税や住民税の負担を軽くできます。 - 運用益
投資信託などで得た利益も非課税で再投資されるため、効率的に資産を増やせます。 - 受取時
将来資金を受け取る際も、大きな控除が適用されます。
ただし、資金の受け取り方には注意が必要です。 「年金」として分割で受け取る場合は「公的年金等控除」「一時金」として一括で受け取る場合は「退職所得控除」の対象となります。
どちらが有利になるかは、ご自身の退職金の有無や他の収入状況によって変わるため、受け取る前にシミュレーションすることが大切です。
また、iDeCoは原則として60歳まで資金を引き出すことができないため、住宅購入や子どもの教育資金といった、老後より手前で必要になる資金の準備には向いていません。
このため、NISAとの使い分けが重要になります。いつでも引き出せる自由度を重視するならNISA、老後資金を着実に、そして節税効果を最大限に活用したいならiDeCo、という視点で優先順位を判断すると良いでしょう。
債券・個人向け国債
債券とは、国や企業へのお金を貸し、利子を受け取る商品です。収益源は利子で、リスクとしては金利変動・信用リスク・価格変動があります。個人向け国債は、国が発行する債券で、個人が買いやすい設計になっています。
個人向け国債には3種類あります。
- 固定3年:3年満期、固定金利
- 固定5年:5年満期、固定金利
- 変動10年:10年満期、半年ごとに金利が見直される変動金利
2025年10月時点の金利は、変動10年型が年1.08%程度、固定5年型が年1.22%程度、固定3年型が年1.01%程度です。最新の金利は財務省の公式サイトで確認できます。
個人向け国債の最大のメリットは、元本と利子の支払いを国が保証している点です。発行から1年経てば中途換金も可能ですが、直近2回分の利子相当額(税引前)×0.79685が差し引かれます。最低金利は年0.05%が保証されています。
利子・満期・価格変動リスク
債券の仕組みを簡単に整理します。
- 利子(クーポン)
半年ごとに受け取れる利息 - 満期償還
満期になると元本が返ってくる - 価格変動
市場金利が上がると債券価格は下がり、市場金利が下がると債券価格は上がる関係
個人向け国債の場合、満期まで保有すれば元本が満額で返ってきます。また、運用中も元本割れすることはありません。ただし中途換金する場合は、中途換金調整額が差し引かれます。
変動10年型は、半年ごとに金利が見直されるため、金利上昇局面では恩恵を受けやすい設計です。逆に金利が下がっても、最低金利0.05%が保証されています。
\ あなたに合うアドバイザーを診断 /
分散投資とポートフォリオ設計の基本

分散投資とは、リスクを和らげるために、複数の資産や地域、時間に分けて投資することです。ここでは、分散の3軸(銘柄・地域・時間)とリバランスの重要性、そしてポートフォリオ(株式・債券・現金)の配分比率を解説します。
初心者が「やり過ぎない基本配分」を理解し、年1回の点検で維持できる状態を目指しましょう。
3つの分散投資(銘柄・地域・時間)
分散投資には、3つの軸があります。
- 銘柄分散
同じ資産クラスの中で複数の銘柄に分ける - 地域分散
日本だけでなく、先進国や新興国にも広げる - 時間分散
定期積立でエントリーのタイミングを分ける
特に、インデックス型の投資信託を活用すれば、1つの商品で手軽に「銘柄の分散」と「地域の分散」を実践できます。そして、積立投資をすることで、「時間の分散」にもなり、3つの分散が実践できます。
例えば、「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」のような商品は、世界中の株式市場の大部分をカバーしており、これ一本で広範な分散投資が可能です。
ただし、分散投資によって損失の可能性が完全になくなるわけではありません。市場全体が下落する局面では、多くの資産価格が同時に下がってしまうこともあります。
分散投資の目的は、あくまで資産価値の大きな変動リスクを和らげることにあると理解しておきましょう。
リバランスの重要性
リバランスとは、想定していた資産配分からのズレを定期的に戻す作業です。
たとえば「株式60%、債券40%」という配分で始めたとします。しかし株式市場が好調だと、株式の値上がりによって「株式70%、債券30%」といった比率になることがあります。すると、想定以上に株式に偏った状態となり、下落時の損失も大きくなってしまいます。
そこで、株式を一部売却して債券を買い増し、元の比率に戻すのがリバランスです。
リバランスの頻度は年1回程度が目安です。あまり頻繁に行うと売買コストがかさみますし、手間もかかります。
実際には、許容する乖離幅(たとえば±5%まではOK)を決めておき、その範囲を超えたときだけ調整する方法が現実的です。
リバランスの実践方法
リバランスには2つのやり方があります。
1つ目は、新規拠出の配分を工夫する方法です。比率が減っている資産を多めに買い付けることで、売却せずに調整できます。
2つ目は、増えすぎた資産を一部売却する方法です。ただしNISA口座で売却すると、その非課税枠は翌年まで復活しないため、タイミングには注意が必要です。
毎年決まった日(例:1月1日)に資産配分をチェックし、乖離幅が±5%を超えていたら調整する、というルールを決めておくと、迷わず実行できます。
株式・債券・現金の配分比率
資産配分に「誰にでも当てはまる正解」はありません。同じ30代でも、独身で収入が安定している人と、子育て中で教育費の備えが必要な人では、適切な配分は異なります。
一般的には「年齢=債券+現金の比率」という目安が語られることもありますが、これはあくまで参考の一つです。
大切なのは、ご自身の収入の安定性、家計の余力、そして「どのくらいの損失なら耐えられるか」というリスク許容度を踏まえて決めることです。
年齢・目的別の配分目安
参考として、3つの典型的なパターンを紹介します。
株式:80%、債券:10%、現金:10%
若く、収入を得られる期間が長いため、一時的に30%程度の下落があっても持ち直す時間があります。そのため株式の比率を高めに設定し、長期的な成長を狙う戦略です。
株式:60%、債券:25%、現金:15%
5〜10年後に教育費が必要になる可能性があるため、やや保守的に年20%程度の下落を想定したリスク管理が現実的です。株式の比率を抑え、債券や現金を増やすことで、必要なタイミングで引き出しやすくします。
株式:50%、債券:30%、現金:20%
老後までの期間が短くなるにつれ、大きな下落から回復する時間的余裕が減るため、年15%程度の下落想定でリスクを抑えます。
これらはあくまで目安であり、ご自身の家計状況や市場環境の変化に応じて、定期的に見直すことが大切です。
資産運用、誰に相談する?
簡単な質問に回答するだけ!
あなたに合った資産運用アドバイザーを紹介
\ 簡単60秒!相談料は無料 /
初心者におすすめしない資産運用手段と注意点

ここでは、初心者におすすめしない資産運用手段として、外貨預金、不動産・REIT、FX・暗号資産の3つの特徴とリスクを解説します。
外貨預金
円を米ドルやユーロなどの外国通貨に換えて預金する商品です。円安が進めば為替差益が、海外の高い金利が適用されればその差額が利益になります。
注意点
一見すると魅力的ですが、予想に反して円高が進めば、元本割れを起こすリスクがあります。また、円と外貨を交換するたびに「為替手数料」がかかり、これが意外とコストになる点も見過ごせません。 さらに「預金」という名前ですが、日本の預金保険制度の対象外となることが多く、万が一の場合に元本が保護されない可能性があることも理解しておく必要があります。
代替案
海外へ投資したいのであれば、複数の国の株式や債券にまとめて投資できる投資信託などを検討するほうが、リスク分散の効果が期待できるでしょう。NISA口座を使えば、得られた利益が非課税になるメリットもあります。
不動産
マンションやアパートなどを直接購入し、家賃収入や売却益を狙うのが不動産投資です。近年、不動産価格の上昇が著しいため注目されていますが、初心者には多くのハードルがあります。
注意点
物件価格だけでなく税金などの諸費用も合わせ、多額の自己資金が必要になります。また、入居者探しや建物の修繕といった管理の手間もかかり、専門的な知識が不可欠です。さらに、売りたいと思ってもすぐに現金化できない「流動性リスク」も大きなデメリットです。
代替案
「それでも不動産から得られる収益には興味がある」という方への代替案が、REIT(リート/不動産投資信託)です。これは、投資家から集めた資金でプロが複数の不動産に投資し、得られた賃料収入などを投資家に分配する仕組みの商品です。 少額から始められ、プロに運用を任せられるうえ、証券取引所でいつでも売買できます。ただし、REITも景気動向などによる価格下落リスクはありますので、まずは資産全体の一部(例えば5〜10%程度)で試すのが賢明です。
FX・暗号資産
FX(外国為替証拠金取引)や暗号資産は、非常に値動きが激しいのが特徴です。「レバレッジ」をかけて自己資金の何倍もの取引ができるため、短期間で大きな利益を狙える可能性があります。
注意点
しかし、その裏返しで損失も一気に膨らむ危険があり、最悪の場合、預けた資金以上の損失を被る「追証(おいしょう)」が発生することも。これらは資産を長期的に「育てる」投資というより、短期的な値動きを予測する「投機」に近いものです。資産形成の土台にするには、極めてリスクが高いと言えるでしょう。
もし挑戦するなら
どうしても興味がある場合は、まず仕組みを徹底的に学び、失っても生活に影響のない少額で試すこと。そして「投資はここまで」という上限額を厳格に決めてから臨むようにしてください。
\ あなたの条件に合うアドバイザーを紹介 /
資産運用の始め方3ステップ
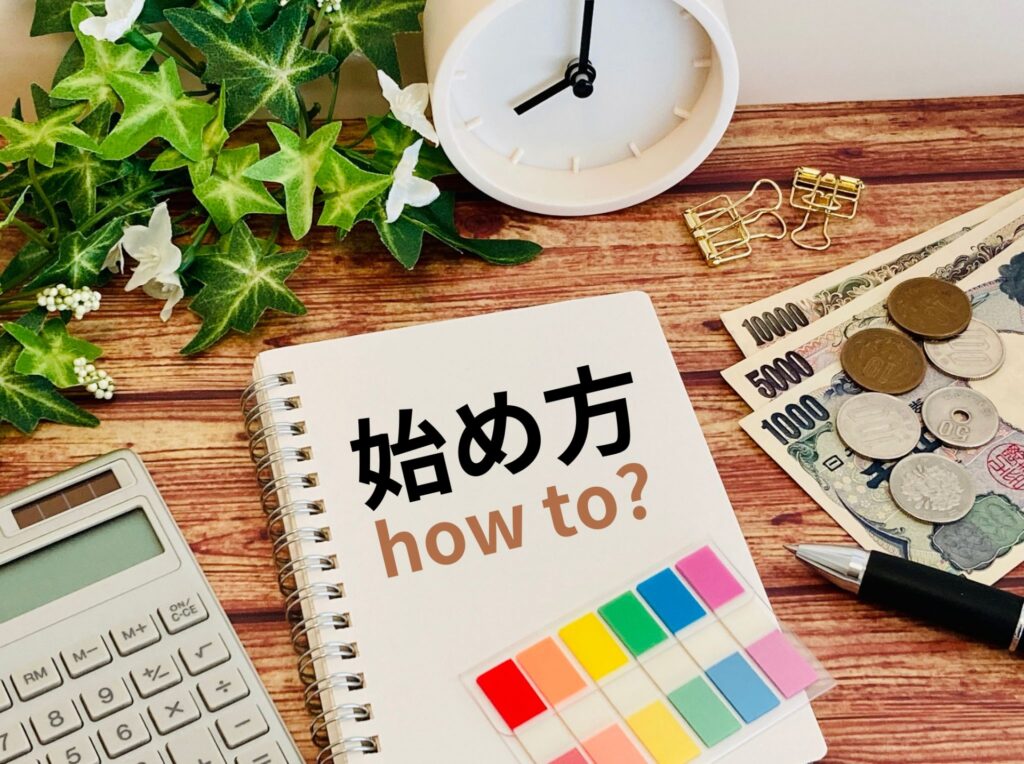
ここからは、実際に資産運用を始めるために、口座開設から商品購入までの具体的な手順を解説します。
ステップ1:証券口座・NISA口座を選ぶ
資産運用を始めるには、まず証券口座の開設が必要です。普通預金口座だけでは投資信託を買うことはできません。また、税制優遇を受けるためにもNISA口座も同時に開設することをおすすめします。多くの証券会社では、証券口座とNISA口座を一度の申込で開設できるため、簡単に手続きできるでしょう。
では、どの証券会社を選べばよいのでしょうか。判断する際は、以下の6つのポイントを比較しましょう。
- 手数料(売買手数料・為替手数料)
- 投資信託の取扱数
- NISA対応の有無
- 自動積立の柔軟性
- アプリの使い勝手
- 入出金のしやすさ
これらの基準を参考に、複数の証券会社を比較検討してみてください。手数料や機能面での違いが大きいため、ご自身の優先順位に合わせて選ぶことをおすすめします。
ステップ2:入金・積立設定・ファンドを購入する
口座開設が完了したら、いよいよ実際の投資をスタートします。手順は以下の通りです。
- ①まず資金を入金する
-
証券口座に投資資金を移します。多くの証券会社では「即時入金サービス」を提供しており、インターネットバンキングから手数料無料で即座に反映されます。普通の銀行振込でも構いませんが、手数料と反映時間を考えると即時入金が便利です。
- ②つみたて投資枠で投資信託を選ぶ
-
次に、どの投資信託を買うかを決めます。初心者の方には、低コストのインデックス型投資信託がおすすめです。商品を選ぶ際は、購入時手数料がゼロ(ノーロード)であること、信託報酬が年0.1%以下程度であることを確認しましょう。
- ③積立の設定をする
-
「毎月いくら、いつ買うか」を設定します。たとえば「毎月10日に3万円」のように、給料日の直後など、資金に余裕があるタイミングを選ぶとスムーズです。金額は無理のない範囲で設定し、後から変更することもできます。
- ④必要に応じて成長投資枠も活用する
-
ボーナス月など、まとまった資金を追加で投資したい場合は、成長投資枠を使った一時金の設定も検討しましょう。ただし、まずはつみたて投資枠での定期積立を優先し、余裕があれば追加する形が無難です。
- ⑤最終確認をして購入開始
-
設定内容を確認し、積立金額、引落口座、積立日、約定日(実際に購入される日)などに間違いがないかチェックします。問題がなければ、自動積立の設定を完了させましょう。これで、毎月自動的に投資が続いていきます。
ステップ3:運用後の定期的な確認と見直しをする
自動積立を設定したら、あとは基本的に放置して構いません。ただし、完全に忘れてしまうのではなく、年1回程度は運用状況を確認する習慣をつけましょう。長期投資では、定期的な点検と必要に応じた修正が、最終的な成果に大きく影響します。
\ あなたの条件に合うアドバイザーを紹介 /
資産運用はプロへの相談がおすすめ
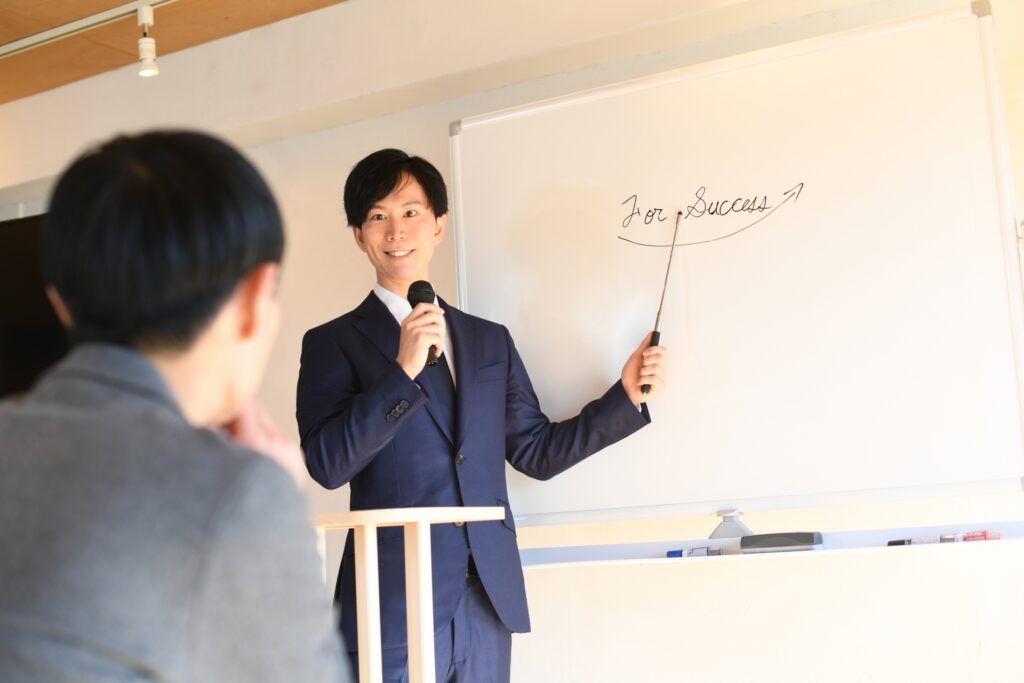
ここまで資産運用の基本的な始め方を解説してきましたが、「自分の収入や家族構成だと、具体的にどうすればいいの?」と迷う方も多いでしょう。そんなときは、プロに相談するのも一つの方法です。
相談先には、証券会社の窓口、FP、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)などがあり、それぞれ特徴が異なります。
ここでは、各相談先の違いや選び方、相談時の注意点について解説します。
プロに相談するメリット
資産運用をプロに相談する最大のメリットは、自分一人では気づきにくい視点やアドバイスが得られることです。具体的には、次のような支援を受けられます。
- 家計全体を見た投資プランの設計
自分で始めようとすると、つい投資だけに目が行きがちですが、プロは収入・支出・貯蓄のバランスを見ながら、無理のない投資額を提案してくれます。生活防衛費を確保した上で、どの程度を投資に回せるかを客観的に判断できます。 - 税制優遇制度の最適な活用方法
NISAとiDeCoをどう組み合わせるか、それぞれにいくら配分するかは、年齢や収入、家族構成によって最適解が変わります。プロは税制面も含めて、あなたに合った制度の使い方を提案してくれます。 - 相場が動いたときの行動ルールがわかる
暴落時にパニックで売却してしまったり、逆に高値で買い増してしまったりといった失敗を避けるため、冷静に判断できるルールを一緒に作ってもらえます。 - 運用計画の見える化
目標利回りのレンジ、必要な積立額、保有コストなどを表やグラフにまとめた資料を作成してもらえます。これらの資料は手元に残るため、後から見返したり、定期的な見直しの際に活用したりできます。
資産運用の相談先|証券会社・FP・IFA
相談先を比較するときの観点を表で整理します。
| 証券会社 | FP(ファイナンシャルプランナー) | IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー) | |
|---|---|---|---|
| 費用 | 基本無料 (商品購入時の手数料のみ) | 有料相談(時間制など) または保険販売の手数料 | 資産残高に応じた手数料 または商品購入時の手数料 |
| 得意領域 | 資産運用全般 | 家計全体の設計 (ライフプランニング) | 資産運用全般 |
| 情報の開示姿勢 | 商品説明は詳しい | ライフプラン表などで 現状を「見える化」 | 手数料体系を明確に提示 |
| 提案の傾向 | 自社で取り扱う商品の販売が中心 | 保険商品の提案が多くなる場合がある | 金融機関から独立しており、 幅広い商品を提案 |
資産運用の相談先を選ぶ際には、上記の表で示した特徴の違いを理解した上で、特に「手数料の明確さ」と「アドバイスの中立性」という2つの観点から判断することが重要です。
相談は無料か、商品購入時の手数料はいくらか、継続的な管理費用は発生するのか、といった費用体系を事前にしっかり説明してくれる相手を選びましょう。説明が曖昧なまま契約すると、後から思わぬ費用が発生する可能性があります。
また、あなたの状況を丁寧にヒアリングした上で、特定の金融商品に偏ることなく、複数の選択肢を比較しながら提案してくれるかどうかも見極めるべき重要な点です。
相談時には強引な勧誘にも注意が必要で、「今日中に決めてください」などと契約を急がされた場合は、一度持ち帰って冷静に検討することをおすすめします。
最近では、Zoomなどを利用したオンライン面談に対応している相談先も増えているため、自宅から気軽に相談したい方は事前に確認してみると良いでしょう。
相談が向いている人・向いていない人
資産運用を専門家と始めるべきか、それとも自分自身で進めるべきか。ご自身の状況に合わせて最適な選択をするために、ここでは判断の目安となるポイントをご紹介します。
向いている人の特徴
次のようなお悩みや状況にある方は、一度専門家に相談してみる価値があるでしょう。
- 新NISAの最適な活用法がわからない方
「つみたて投資枠」と「成長投資枠」を自分の状況に合わせてどう使い分ければ良いか、具体的なプランを立てられない。 - 市場が大きく下落した際の対応に不安がある方
暴落時に狼狽して売却してしまいそうで、冷静な判断を保つ自信がない。 - 家計全体のバランスを見ながら投資計画を立てたい方
教育費や住宅ローンといった将来の支出と両立させながら、無理のない投資額をどう設定すればよいか悩んでいる。
専門家に相談することで、現状の客観的な分析や、ご自身に合った資産配分の提案、具体的な設定のサポートなどを得ることができます。
向いていない人の特徴
一方で、次のような方は、必ずしも相談は必要なく、ご自身での学習や少額での実践から始めるのが適しているかもしれません。
- 短期的な売買で利益を追求したい方
専門家によるアドバイスは長期的な資産形成を前提としているため、投資スタイルや目的が合わない可能性があります。 - ご自身で情報収集し、投資判断ができる方
すでに十分な知識があり、リスクを正しく理解した上で、自己責任で投資を進められる。
このような方は、まず金融庁や証券会社が提供している学習コンテンツを活用したり、無理のない範囲の少額から投資を試してみたりすることをおすすめします。
\ あなたの条件に合うアドバイザーを紹介 /
初心者が失敗しやすいパターンと回避策

資産運用を始めたばかりの頃は、誰もが判断に迷ったり、思わぬ失敗をしたりするものです。
ここでは、初心者がよく陥りがちな失敗パターンと、その対策について解説します。
よくある3つの失敗パターン
まずは、初心者が陥りやすい代表的な失敗を3つ見ていきましょう。
SNSの情報を鵜呑みにして衝動買いしてしまう
「今買わないと損!」「この銘柄は確実に上がる!」といったSNSやネット掲示板の情報を見て、つい焦って購入してしまうケースです。しかし、そうした情報の多くは根拠が不確かだったり、発信者に別の目的があったりします。リスクや手数料を確認せずに買ってしまうと、後から「こんなはずじゃなかった」と後悔することになります。
一つの銘柄や資産に集中投資してしまう
「この商品は絶対に値上がりする」と思い込んで、ポートフォリオの大部分を一つの銘柄に集中させてしまう失敗です。確かに当たれば大きく増えますが、外れたときの損失も大きくなります。分散投資の基本を忘れて、ギャンブルのような投資になってしまうのです。
相場が下がったときに積立をやめてしまう
価格が下落すると、「このまま続けたら損失が膨らむのでは」と不安になり、積立を停止してしまうパターンです。しかし、積立投資の本質は、安いときにたくさん買うことで平均購入単価を下げることにあります。下落時こそチャンスなのに、感情的に判断してやめてしまうと、その恩恵を受けられません。
失敗を回避する具体的な方法
投資で失敗してしまう方に共通しているのは、「焦りなどの感情的な判断」や「その場の雰囲気での行動」です。これを防ぐには、最初に長続きできる「仕組み」を作ってしまい、あとは淡々と続けることが最も効果的です。
ここでは、感情に振り回されずに資産運用を続けるための、3つの具体的な対策をご紹介します。
① 最初に「マイルール」を決めて、あとは「自動」におまかせ
まず、自分だけの投資ルールを紙に書き出してみましょう。難しく考える必要はありません。例えば、こんなルールです。
- 「SNSの情報だけで買わず、必ず商品の説明書を確認する」
- 「一つの商品への集中投資は避ける」
- 「家計が苦しくならない限り、決めた積立は止めない」
ルールを決めたら、証券会社のサイトにある簡単な診断ツールで自分に合った資産の組み合わせを考え、すぐに「自動積立」を設定しましょう。
設定さえしてしまえば、あとは毎月機械的に買い付けてくれるため、「今月は買うべきかな?」「どのタイミングがいいんだろう?」と悩む必要がなくなります。考える時間が長いほど感情に流されやすくなるため、最初に仕組みを整えて自動化してしまうのが成功のコツです。
② チェックと見直しは「年に1回」だけでOK
一度設定したら、毎日株価をチェックする必要はありません。むしろ、頻繁に売買すると手数料がかさんだり、焦りから良くない判断をしてしまったりする原因になります。
年に1回、誕生日などの決まった日に資産全体のバランスを確認するだけで十分です。
例えば「株式60%、債券40%」と決めていたのに、株式が値上がりして「70%:30%」のようにバランスが崩れていたら、元の比率に戻す微調整(リバランス)を行いましょう。この手間をかけないスタイルが、冷静に運用を続ける秘訣です。
③ 感覚ではなく「数字」でシンプルに確認する
年に1回のチェックでは、難しい分析は不要です。感覚で判断するのではなく、以下のポイントを数字で確認する習慣をつけましょう。
- 手数料(コスト)
今持っている商品よりも、もっと手数料の安い良い商品が出ていないか? - 運用成績
現在、どれくらいの利益(または損失)が出ているか? - NISA枠の利用状況
年間の非課税枠をあとどれくらい使えるか?
これらの数字をメモしておくと、翌年に見比べたときに資産の変化が分かりやすくなります。
\ あなたの条件に合うアドバイザーを紹介 /
まとめ

資産運用で成功するための基本は、決して難しいことではありません。
それは「つみたて投資枠」を使い、手数料の安いインデックス投資信託を自動で積み立て、あとは年に一度だけ見直すというものです。この基本さえ押さえれば、初心者の方でも迷うことなく資産形成をスタートできます。
この記事を読んだら、まずは次の4つを決めてみましょう。
- どの証券会社で口座を開くか
- 毎月いくら積み立てるか
- どの投資信託にするか
- いつから始めるか
この設定さえ完了すれば、あとは基本的に見守るだけで大丈夫です。
もし「自分一人で決めるのは、やっぱり不安…」と感じるなら、資産運用アドバイザーのような専門家への相談も有効な選択肢です。家計全体のバランスを見ながらの投資プランの作成や、相場が大きく下がったときのフォローなど、十分なサポートが受けられます。
安心して次の一歩を踏み出すために、まずは資産運用アドバイザーに相談してみましょう。
\ あなたの資産を任せられるプロがいる /
FAQ

\ あなたの資産を任せられるプロがいる /
出典一覧
- 本記事の情報は2025年10月時点のものです。制度や金利は変更される可能性がありますので、最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。